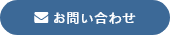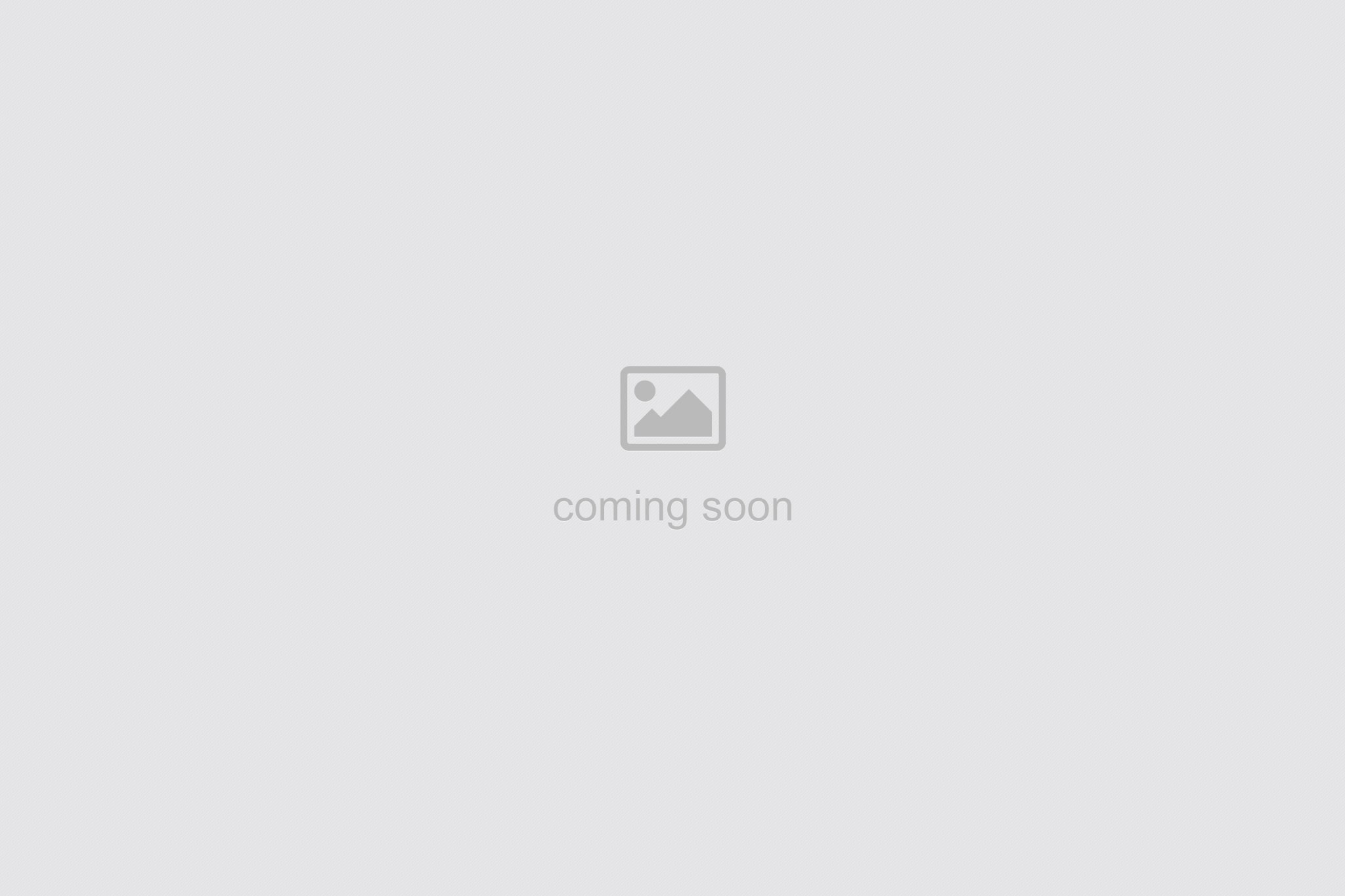ご あ い さ つ
昭和27(1952)年に発足した日本修学旅行協会は、平成25(2013)年4月より公益財団法人として歩みはじめました。
平成31(2019)年後半からおよそ2年半に及ぶコロナ禍により、教育旅行は中止や延期などが相次ぎ大きな打撃を受けましたが、当協会が担っております公益事業は滞ることなく順調に進めることができました。 このことは、ひとえに皆様からいただきました当協会への厚いご支援の賜物と存じ心から感謝申し上げます。ありがとうございました。
当協会では、教育旅行を、学習指導要領において「旅行・集団宿泊的行事」として位置づけられている学校の教育活動のうち、修学旅行を主とするものととらえています。日本の優れた教育文化として定着しております修学旅行は、生徒たちが「平素と異なる生活環境にあって、見聞を広め、自然や文化などに親しむ」貴重な学びの場であるとともに「集団生活の在り方や公衆道徳などについての体験を積む」うえでの大切な機会であり、社会のグローバル化に対応する国際理解や国際交流の促進にも大きな役割を果たしています。
修学旅行を主とする教育旅行のさらなる充実と発展を図るため、当協会では、学校教育により「持続可能な社会の創り手」を育てるという新学習指導要領の主旨を踏まえるとともに、教育旅行を「探究的な学習」を展開するにふさわしい場として、これまでの歴史学習・平和学習に加え、SDGsに関わる地域の多様な取組や地球規模で自然や環境・人々の暮らしを考えるジオツーリズム、エコツーリズム、被災地の経験から学ぶ震災学習や防災・減災学習、農山漁村での体験的な活動やキャリア教育にもつながる産業観光など、新たな分野も積極的に取り上げていきたいと考えています。
また、未だコロナ禍以前の状況に回復していない海外修学旅行の復活を期して、アジアや北米、オセアニアなどの国や地域における教育旅行の適地を紹介し、あわせて訪日旅行の受け入れについても積極的に取り組んでいくつもりです。
デジタル版も好評を得ております当協会発行の月刊誌「教育旅行」や教育旅行年報「データブック」において、修学旅行を主とする教育旅行の動向や実態、優れた実践例や教育旅行の適地などに関する情報を発信するとともに、各種セミナーでの講演や新たなプログラムづくりへの助言などを通して教育旅行誘致による地域の振興にも資するように努めていきます。
新型コロナの位置づけが5類に移行したこともあり、教育旅行もコロナ禍以前のように活発に実施されるようになっています。日本修学旅行協会は、今年度も時代のニーズと学校教育の動向を踏まえ、国内外の教育旅行の一層の発展を図るとともに、それを通じて地域の活性化にも貢献すべく事業を進めてまいります 。
これまで同様、皆様のご指導とご支援を何卒よろしくお願い申し上げます 。