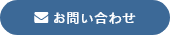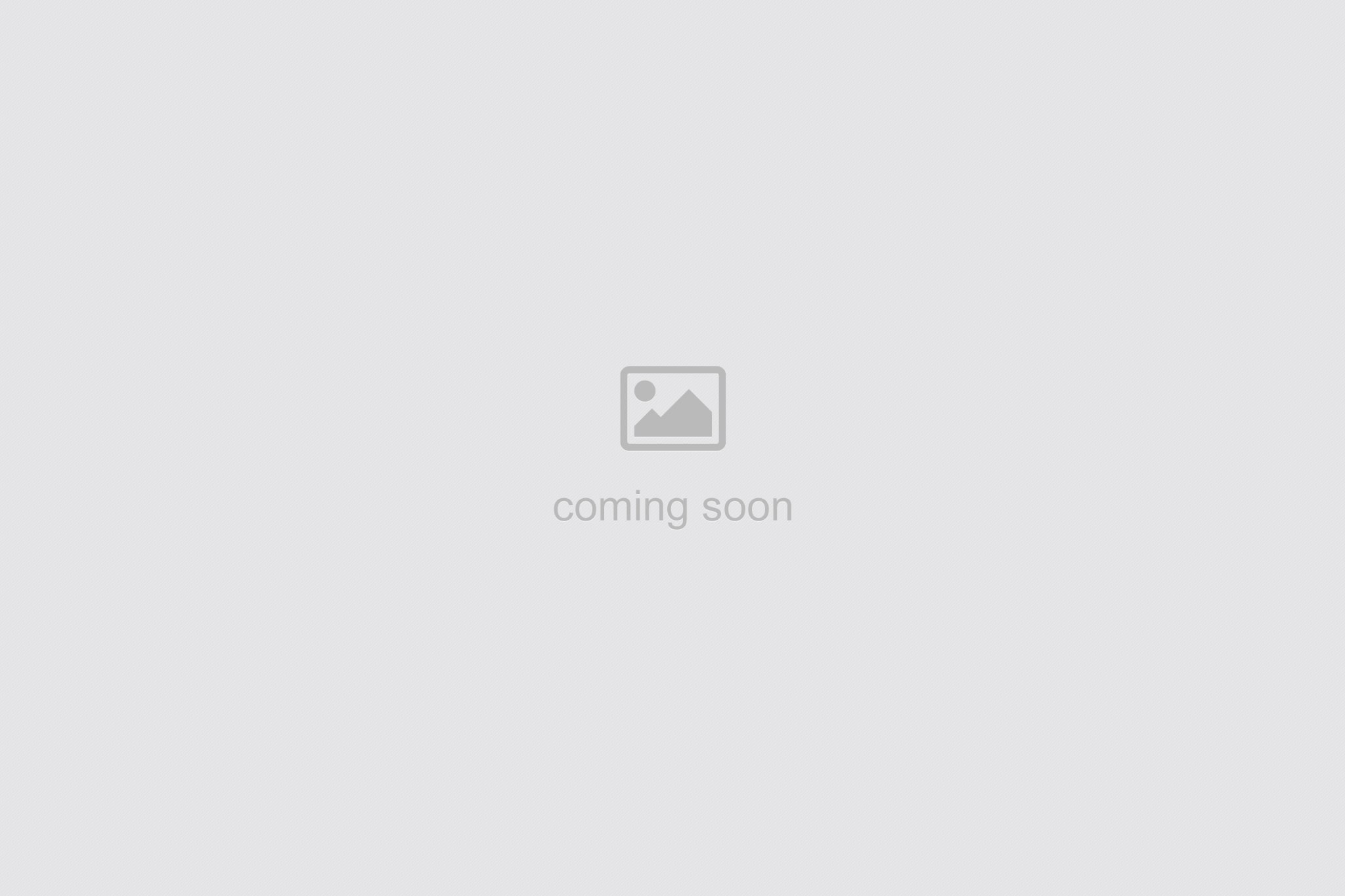視察レポート
京都市内から意外に近い「海の京都」での探究学習プログラム(2025年2月号掲載)
2025-02-05
NEW
文・写真=(公財)日本修学旅行協会 理事長 竹内 秀一
月刊「教育旅行」2025年2月号掲載
※本記事中の情報は執筆当時のもので、その後変更されている場合があります。
最新情報は問い合せ先にご照会ください。
※本記事中の情報は執筆当時のもので、その後変更されている場合があります。
最新情報は問い合せ先にご照会ください。
京都は、中学校の修学旅行の旅行先として常にトップを占め、高校の修学旅行の旅行先としても上位に位置している。ところが最近では、外国人観光客の急増などによって京都市内のメインエリアが大混雑となってしまったため、旅行先の変更を考える学校も現れ始めている。
しかし、市内のほかにも、大きな「学び」の効果が期待されるスポットが豊富にあるのが京都だ。京都府では、今、「もうひとつの京都」として「海の京都」(京都府北部)、「森の京都」(京都府中部)など多様なエリアの魅力を発信している。
今回は、京都府が主催する首都圏の高校の先生方を対象とした「海の京都」エリアの視察会に同行させていただいた。(▼以下は参加された先生方の感想)
しかし、市内のほかにも、大きな「学び」の効果が期待されるスポットが豊富にあるのが京都だ。京都府では、今、「もうひとつの京都」として「海の京都」(京都府北部)、「森の京都」(京都府中部)など多様なエリアの魅力を発信している。
今回は、京都府が主催する首都圏の高校の先生方を対象とした「海の京都」エリアの視察会に同行させていただいた。(▼以下は参加された先生方の感想)
サンガスタジアムでドローンサッカーを体験
サッカーJ1リーグ、京都サンガFCのホームスタジアム・サンガスタジアムby KYOCERA は、京都市内からバスで約40分、JR亀岡駅のすぐそばにあり、保津川下りの乗船場も近い。このスタジム1階にドローンサッカーの常設アリーナが設けられている。
ドローンサッカーとは、ドローンが組み込まれた網目状のボールをコントローラーで操縦し、空中に吊り下げられたリングを通すことで得られる点数を競い合う競技。5人で1チームを構成するが、得点できるのはそのうちの一人だけ。あとの4人は、相手チームのボールの動きを妨害したり仲間を助けたりする。
ボールを操縦するコントローラーは、ゲーム機のものとほぼ同じなので、生徒たちは操作にはすぐに慣れるだろう。相手チームに勝つためには、戦略や戦術を練る話し合いと、それぞれが任された役割を確実に果たすチームワークが大切になる。チームビルディングには最適の体験活動だが、何よりも、健常な生徒と障がいのある生徒とが、一緒のチームになって楽しむことができるのがこのスポーツの優れたところだ。
▼勤務校では運動に苦手意識のある生徒も多く、スポーツ大会の種目も配慮している。そのため、年齢や性別、障がいの有無、運動の得意・不得意等に関わらず、誰でも行うことのできるドローンサッカーは大変魅力的に感じた。チームでの協力や戦略を練ることも必要となる競技で、新たな形のチームスポーツとして学校教育の中で取り入れていくことができる。
ドローンサッカーとは、ドローンが組み込まれた網目状のボールをコントローラーで操縦し、空中に吊り下げられたリングを通すことで得られる点数を競い合う競技。5人で1チームを構成するが、得点できるのはそのうちの一人だけ。あとの4人は、相手チームのボールの動きを妨害したり仲間を助けたりする。
ボールを操縦するコントローラーは、ゲーム機のものとほぼ同じなので、生徒たちは操作にはすぐに慣れるだろう。相手チームに勝つためには、戦略や戦術を練る話し合いと、それぞれが任された役割を確実に果たすチームワークが大切になる。チームビルディングには最適の体験活動だが、何よりも、健常な生徒と障がいのある生徒とが、一緒のチームになって楽しむことができるのがこのスポーツの優れたところだ。
▼勤務校では運動に苦手意識のある生徒も多く、スポーツ大会の種目も配慮している。そのため、年齢や性別、障がいの有無、運動の得意・不得意等に関わらず、誰でも行うことのできるドローンサッカーは大変魅力的に感じた。チームでの協力や戦略を練ることも必要となる競技で、新たな形のチームスポーツとして学校教育の中で取り入れていくことができる。
天橋立で地理・歴史そして自然環境の保全を学ぶ

天橋立「股のぞき」
日本三景の一つ天橋立は、京都市内から高速道路を利用すれば、およそ100分あまりで行くことができる。その全景を高所から望む「股のぞき」が有名だが、それができる天橋立ビューランドへは、麓からリフトかモノレールを利用して、6~7分で到着する。
リフトを降り、初めて眼下に天橋立を見た先生たちからは、「オーッ」という声が上がった。きっと生徒たちも同様だと思う。「股のぞき」して展望台から眺める天橋立は、天に舞い上がる龍のように見える。この景観は「飛龍観」と呼ばれているそうだが、十分に納得できる。
天橋立は、地理の授業では砂州の典型として取り上げられ、日本史の授業でも雪舟の水墨画「天橋立図」を扱うことが多い。砂州の形成過程を考えたり、「天橋立図」に描かれた景観と実際のそれとを比較したりと、教科と関連させて学ぶこともできる。天橋立の松林の中を歩きながら、美しい景観が現在まで保たれてきた背景にある環境保全の取り組みについても考えてみたい。
リフトを降り、初めて眼下に天橋立を見た先生たちからは、「オーッ」という声が上がった。きっと生徒たちも同様だと思う。「股のぞき」して展望台から眺める天橋立は、天に舞い上がる龍のように見える。この景観は「飛龍観」と呼ばれているそうだが、十分に納得できる。
天橋立は、地理の授業では砂州の典型として取り上げられ、日本史の授業でも雪舟の水墨画「天橋立図」を扱うことが多い。砂州の形成過程を考えたり、「天橋立図」に描かれた景観と実際のそれとを比較したりと、教科と関連させて学ぶこともできる。天橋立の松林の中を歩きながら、美しい景観が現在まで保たれてきた背景にある環境保全の取り組みについても考えてみたい。
近くにある智恩寺は、日本三文殊の一つに数えられる古刹。江戸時代に再建された壮大な禅宗様の山門や「天橋立図」にも描かれた室町時代創建の多宝塔など、建築物に見るべきものが多い。参道で売られている「知恵の餅」は、生徒たちにも人気だと思う。智恩寺の先、天橋立に渡る小天橋(しょうてんきょう)は、船が通るたびに90度旋回する廻船橋。珍しい橋なので、ぜひ見ておきたい。
▼あまりにも有名な場所であるが、その美しさはまさに百聞は一見にしかずで、ぜひ現地の展望台に行かせたい。近年のイグ=ノーベル賞でも話題になった股のぞきも、単に写真を天地逆にすればわかるというものではなく、実際に自分で試してみてその面白さを知ることができる。また、天橋立はその成立過程も特殊であり、実際に歩いてみることで地理の学習にも活かすことができる。
舞鶴の浜で漁師さんと学ぶ海のSDGs
天橋立から舞鶴までがバスでおよそ1時間。その少し先に野原漁港と遠浅で水がきれいな野原海水浴場がある。ここでは、干物づくり体験と、海洋プラスチックについてレクチャーとマイクロプラスチック採取などの体験を通して学ぶプログラムが用意されている。
干物づくりは、野原地区の主要産業だ。地元漁師の女将さんたちの指導を受けながら、今回は、カマスとシロイカを2尾ずつ開いた。なまの魚を触ったことのない生徒も多いと思うが、先生たちも同様で悪戦苦闘の様子。開いた魚の乾燥は機械で行うが、それ以外は手作業になる。「食育」にも繋げることができるので、多くの生徒にチャレンジしてほしい体験活動だ。できた干物を、翌日までに宿舎などに届けてもらえるのも嬉しい。
海洋プラスチックに関するレクチャーは、地元の漁師さんが講師になって行う。漁業と海洋資源の保全との両立、海洋ゴミについての話は、実際に漁に携わっている方々だけにとてもリアルだ。
浜辺は一見するととてもきれいだが、目を凝らすと赤や緑、黄色といった色とりどりの小さなプラスチックのかけらが無数にあることがわかる。採取を体験させながら、それらがもとは何だったのか、生徒たちに考えさせてみたい。流れ着いたペットボトルを、国や地域別に分別する作業も興味深かった。作業前は、外国のものが多いだろうと思っていたが、実は圧倒的に日本のものが多い。日本のペットボトルの原料としての再利用率は20%ほどで、OECD加盟国中の下位だという。
マイクロプラスチックを摂取した魚には、消化器障害や繁殖力の低下といった影響が出ているそうだ。それを蓄積した魚が人間の口に入るというのも恐ろしい。
▼今回は実際に漁師の方とともにマイクロプラスチックを分析しながら拾ったり、ペットボトルを実際に仕分けしながら、どこからの流出量が多いのかを考えた。教室で教師が画像を見せて教えるよりも、実際に地元の漁師さんから今抱えている問題を生の声で聴いたり、実際に手に取って感じることで、生徒は感じるものや考えることは大いにあると感じた。
浜辺は一見するととてもきれいだが、目を凝らすと赤や緑、黄色といった色とりどりの小さなプラスチックのかけらが無数にあることがわかる。採取を体験させながら、それらがもとは何だったのか、生徒たちに考えさせてみたい。流れ着いたペットボトルを、国や地域別に分別する作業も興味深かった。作業前は、外国のものが多いだろうと思っていたが、実は圧倒的に日本のものが多い。日本のペットボトルの原料としての再利用率は20%ほどで、OECD加盟国中の下位だという。
マイクロプラスチックを摂取した魚には、消化器障害や繁殖力の低下といった影響が出ているそうだ。それを蓄積した魚が人間の口に入るというのも恐ろしい。
▼今回は実際に漁師の方とともにマイクロプラスチックを分析しながら拾ったり、ペットボトルを実際に仕分けしながら、どこからの流出量が多いのかを考えた。教室で教師が画像を見せて教えるよりも、実際に地元の漁師さんから今抱えている問題を生の声で聴いたり、実際に手に取って感じることで、生徒は感じるものや考えることは大いにあると感じた。
舞鶴引揚記念館で考える「戦争と平和」
日清戦争後に鎮守府が置かれ、日本海側唯一の軍港を要する都市として発展した舞鶴。赤レンガ倉庫群をはじめ、今もその面影を色濃く残しているまちだ。第二次世界大戦終結後、舞鶴港は、シベリアや旧満洲(中国東北部)、朝鮮などからの引揚者を迎え入れる引揚港に指定され、昭和二〇(1945)年からその役割を終える昭和三三年までに、66万人余りの人々がここに上陸した。
JR東舞鶴駅からバスで約20分北上すると舞鶴引揚記念館がある。ここには、日本史の教科書でも多くは触れられていない引き揚げやシベリア抑留について学び、考えるための貴重な資料が収蔵・展示されている。
常設展示室の最初のゾーンには、ソ連によって連行・抑留され、厳しい労働を強いられた軍人・軍属の生活がわかる実物資料が展示されている。それらを代表するのが「白樺日誌」だ。抑留者が、白樺の木の皮に空き缶を加工したペンを使い、煤を溶かしたインクで日々の想いを和歌にして綴ったもので、ユネスコの「世界の記憶」に登録されている。自由にものを手に入れられないラーゲリ(収容所)で、抑留された人々は、様々に工夫して日用品や将棋の駒などの娯楽用品を手作りしていた。辛い毎日を生き延びようとする切実な思いが伝わってくる。
実物大のマネキンで再現されたラーゲリでの生活の一コマは、食事として支給された小さな黒パンを切り分けている場面。天秤ばかりで計って公平に分けようとしている様子が生々しい。「抑留生活体験室」にはラーゲリの小屋が再現されていて、狭いベッドに寝たり、衣類に触ったりする体験もできる。
壁面に、引き揚げに使用された船の模型がずらりと展示されている。船内でも多くの人が亡くなったという。舞鶴港で近親者や知人の帰還を待つ人々の姿なども実物資料やパネル展示で紹介されている。記念館のある公園の展望台からは、復元された引揚桟橋が展望できるそうだ。
JR東舞鶴駅からバスで約20分北上すると舞鶴引揚記念館がある。ここには、日本史の教科書でも多くは触れられていない引き揚げやシベリア抑留について学び、考えるための貴重な資料が収蔵・展示されている。
常設展示室の最初のゾーンには、ソ連によって連行・抑留され、厳しい労働を強いられた軍人・軍属の生活がわかる実物資料が展示されている。それらを代表するのが「白樺日誌」だ。抑留者が、白樺の木の皮に空き缶を加工したペンを使い、煤を溶かしたインクで日々の想いを和歌にして綴ったもので、ユネスコの「世界の記憶」に登録されている。自由にものを手に入れられないラーゲリ(収容所)で、抑留された人々は、様々に工夫して日用品や将棋の駒などの娯楽用品を手作りしていた。辛い毎日を生き延びようとする切実な思いが伝わってくる。
実物大のマネキンで再現されたラーゲリでの生活の一コマは、食事として支給された小さな黒パンを切り分けている場面。天秤ばかりで計って公平に分けようとしている様子が生々しい。「抑留生活体験室」にはラーゲリの小屋が再現されていて、狭いベッドに寝たり、衣類に触ったりする体験もできる。
壁面に、引き揚げに使用された船の模型がずらりと展示されている。船内でも多くの人が亡くなったという。舞鶴港で近親者や知人の帰還を待つ人々の姿なども実物資料やパネル展示で紹介されている。記念館のある公園の展望台からは、復元された引揚桟橋が展望できるそうだ。
記念館では近隣の中学生・高校生が語り部となって展示物を解説してくれる(授業のない日のみ)。戦時を体験された方々から直接お話を聴く機会が少なくなっている現在、修学旅行での平和学習をどのように進めていくかが大きな課題となっている。修学旅行生と同年代の生徒がこうした活動をしていることを知ること自体が、生徒たちにとっては大きな刺激になるだろう。
戦争を多角的に捉えていくうえで、引き揚げと抑留に焦点を当てた舞鶴引揚記念館は貴重な学びの施設だ。ぜひ多くの生徒たちにここに来て学んでほしい。
▼中学生や高校生からなる「学生語り部」による展示案内が、本資料館視察の最大の魅力である。用意された原稿に基づく言葉ではなく、深く理解したうえで説明していることが、その言葉遣いや視線の運び方からうかがわれた。戦争の時代の記憶の継承は各地域での課題となっている。舞鶴での学生語り部の取り組みからは、大学生、高校生、中学生と様々な世代が橋渡しする形で、地域の歴史を自分事として捉える新しい世代を担い手とした平和教育のモデルを示されたように思う。
今の京都では計画通りの活動ができない、という声を学校から多く聞くようになった。しかし、これは京都市内の人気スポットのこと。京都全体を見渡せば、混雑することもなく、しっかりと「学び」の旅ができる地域は少なくない。
今回、視察させていただいた天橋立や舞鶴など「海の京都」エリアは、遠くに感じられるが、高速道路を利用すれば市内から100分あまりと意外に近い。このエリアには、平和学習、自然環境学習、SDGs学習のほか、赤レンガ建築を巡る舞鶴のまちあるきなど、学校が求めている多彩なプログラムが実施できる場所や施設が集中している。それぞれの場所や施設で一度に活動できる人数は多くないが、探究学習で実施される分散学習には適したエリアだと考える。
また、活動拠点とするに相応しい宿泊施設としては、メルキュール京都宮津リゾート&スパがある。宮津湾を望む高台にあり、洋室・和室を備え、温泉大浴場もある大人数が宿泊できるホテルだ。
京都市内での活動は外せないかもしれないが、学校には、新たな訪問先として「海の京都」をぜひおすすめしたい。
【問い合せ先】
京都府商工労働観光部 観光室
京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町
TEL:075―414―5239
e-mail:kanko@pref.kyoto.lg.jp
戦争を多角的に捉えていくうえで、引き揚げと抑留に焦点を当てた舞鶴引揚記念館は貴重な学びの施設だ。ぜひ多くの生徒たちにここに来て学んでほしい。
▼中学生や高校生からなる「学生語り部」による展示案内が、本資料館視察の最大の魅力である。用意された原稿に基づく言葉ではなく、深く理解したうえで説明していることが、その言葉遣いや視線の運び方からうかがわれた。戦争の時代の記憶の継承は各地域での課題となっている。舞鶴での学生語り部の取り組みからは、大学生、高校生、中学生と様々な世代が橋渡しする形で、地域の歴史を自分事として捉える新しい世代を担い手とした平和教育のモデルを示されたように思う。
今の京都では計画通りの活動ができない、という声を学校から多く聞くようになった。しかし、これは京都市内の人気スポットのこと。京都全体を見渡せば、混雑することもなく、しっかりと「学び」の旅ができる地域は少なくない。
今回、視察させていただいた天橋立や舞鶴など「海の京都」エリアは、遠くに感じられるが、高速道路を利用すれば市内から100分あまりと意外に近い。このエリアには、平和学習、自然環境学習、SDGs学習のほか、赤レンガ建築を巡る舞鶴のまちあるきなど、学校が求めている多彩なプログラムが実施できる場所や施設が集中している。それぞれの場所や施設で一度に活動できる人数は多くないが、探究学習で実施される分散学習には適したエリアだと考える。
また、活動拠点とするに相応しい宿泊施設としては、メルキュール京都宮津リゾート&スパがある。宮津湾を望む高台にあり、洋室・和室を備え、温泉大浴場もある大人数が宿泊できるホテルだ。
京都市内での活動は外せないかもしれないが、学校には、新たな訪問先として「海の京都」をぜひおすすめしたい。
【問い合せ先】
京都府商工労働観光部 観光室
京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町
TEL:075―414―5239
e-mail:kanko@pref.kyoto.lg.jp